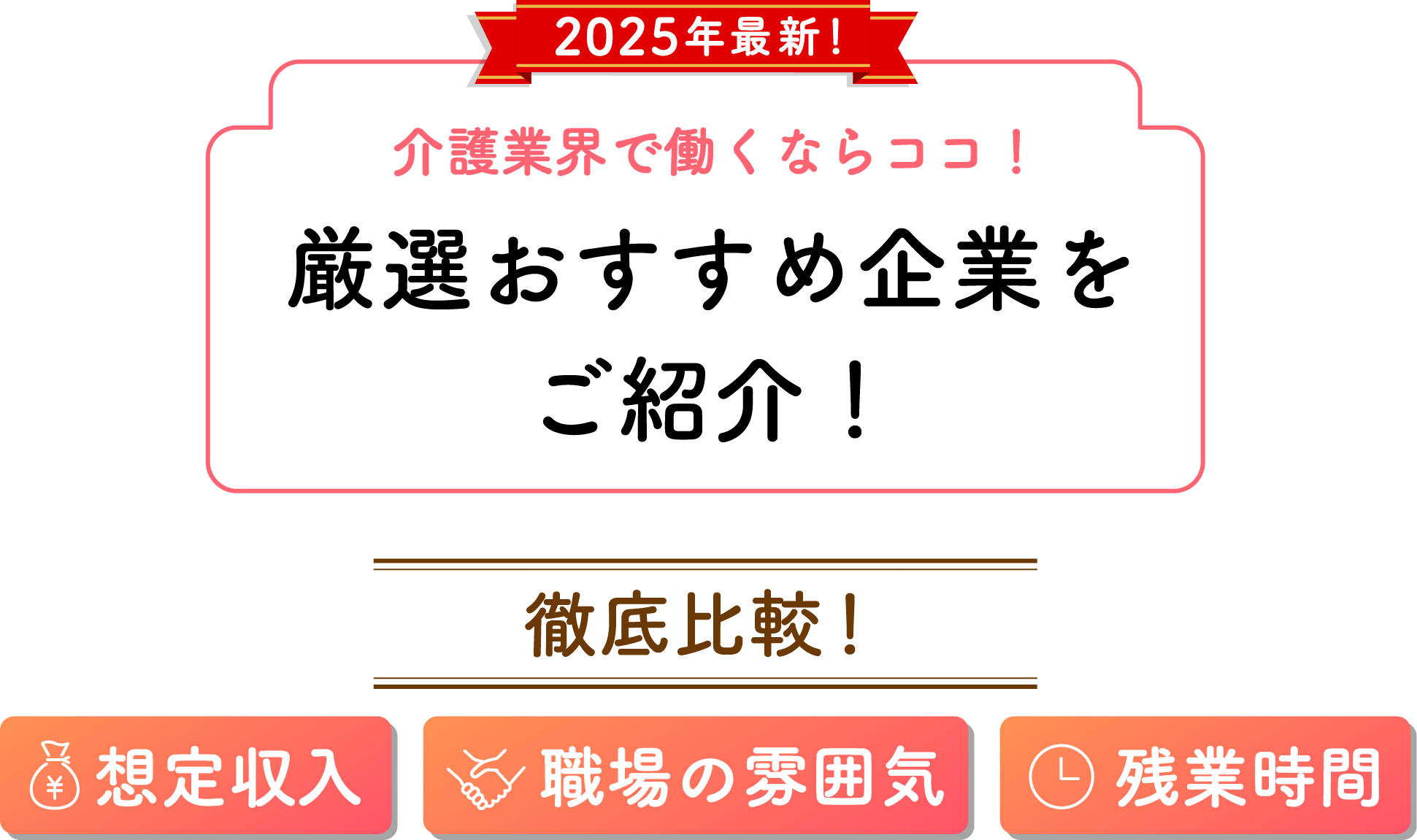日々の介護業務の中で、先輩職員やケアマネジャーが「介護」や「介助」と言っているのを聞き、明確な違いが気になる方もいるのではないでしょうか。
実際「介護」と「介助」には、意味に明確な違いがあります。
そこで本記事では、それぞれの意味や具体的な内容について解説します。
また、記事の後半では、介護や介助に共通して重要な視点や注意点もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
介護と介助の違い
「介護」と「介助」という2つの言葉は、よく混同されやすいですが、プロの介護士はしっかりと使い分けをしています。
まずは「介護」と「介助」の意味の違いについて、詳しく解説していきます。
介護とは
「介護」とは、高齢者や障害者の日常生活を支えるサポートを幅広く指します。
疾患や障がい、加齢などによって身の回りの手助けが必要な方に対し、適切なお手伝いを行うことが介護の基本です。
この「介護」には、身体的なサポートのみならず、声かけや会話といった精神面の支援も含まれます。
また、利用者が自分でできることは見守るというスタンスも重要でしょう。
過度に手伝うと、活動量や生活機能の低下につながってしまうためです。
介護の目的は、利用者の社会生活の安定と、生活の質の向上、自立支援のためのサポートを行うことです。
<身体介護>
介護業務において、利用者の身体に直接触れる必要のあるものが「身体介護」です。
例えば、更衣や移乗、起き上がり動作のサポートなどが当てはまります。
前述のとおり、利用者の活動すべてを介護士が行うのではなく、利用者が持っている残存機能を生かすために、サポートの方法やお手伝いの程度を見極めることも大切です。
<生活援助>
掃除や洗濯、調理といった家事の代行は「生活援助」と呼ばれます。
生活機能の維持のために、ご自身でできる部分は行ってもらいながら、必要な部分だけを援助します。
例えば、洗濯を干したり、取り込んだりするのは介護士が行い、取り込んだ服を畳むのは利用者にしてもらうなど、利用者のADL(日常生活動作)を損なわないようにすることが大切です。
<そのほかの支援>
身体介護や生活援助以外にも、精神面のケアやレクリエーションの実施など、介護士の仕事は多岐に渡ります。
コミュニケーションを取ったり、悩みを傾聴したりすることも、利用者のストレスケアとして重要です。
このような余暇活動の充実や、精神的な安定を図るサポートも、介護の重要な一つの役割といえるでしょう。
介助とは
「介助」とは、介護を実施するための具体的な行為のことです。
身体介護であれば、排泄におけるオムツ交換やトイレでのサポート、入浴における更衣や移乗、洗身のお手伝いなどが挙げられます。
介助において大切なのは、利用者の残存機能を見極め、必要なお手伝いの方法を選択することです。
例えば、できる限りオムツではなくトイレで排泄を行う、利用者ご本人の立ち上がる能力を生かすために最小限のサポートにとどめるといったことが必要となるでしょう。
介護者は、そのための介助技術を習得することが大切です。
身体介護として行う6つの介助
身体介護は、大きく分けて6つに分けられます。
実際のところ介護初心者は、移乗介助や排泄介助から教わることが多いのではないでしょうか。
それでは、一つずつご紹介していきましょう。
排泄介助
排泄介助とは、トイレでの介助やオムツ交換、尿器などを利用する排泄のお手伝いを指します。
トイレへの移乗や、ズボンやパンツの上げ下ろしが困難な方に対しての介助や、尿意や便意のコントロールが困難でオムツ交換を必要としている方へのサポートが含まれます。
排泄介助では、単に排泄時のお手伝いをするのみならず、排泄物の量や色、頻度などの情報を記録し、排泄のリズムや病理的な異常がないかを確認することも大切な役割です。
また、デリケートな部分の介助であるため、利用者ご本人の羞恥心への配慮や、可能な限りのプライバシー保護が求められます。
入浴介助
入浴介助は、利用者お一人での入浴が困難な方に提供される介助です。
入浴には、心身のリフレッシュとともに、身体を清潔に保つことにより、皮膚トラブルや感染症を予防する役割があります。
また、全身の皮膚状態を確認できる機会でもあり、異常があれば医師や看護職員に伝えることも重要です。
さらに、一般的な浴槽への入浴のみならず、ストレッチャーのままの入浴や、チェアーごと入浴できる機械浴(特殊浴)も、入浴介助には含まれます。
食事介助
上肢の機能や認知能力の低下により、自力ではスプーンや箸を口元に持っていけない方には、食事介助が必要です。
食事のすべてを介助する場合もあれば、食事の後半に疲労が見られたあたりから、一部の介助のみを行う場合もあります。
また、提供されたおかずなどの食事を食べやすいよう、細かく切り分ける行為も食事介助の一環です。
歩行介助
高齢になると、ほんの少しの段差でつまずいたり、バランスを崩しやすくなったりします。
歩行介助では、杖や歩行器を利用して歩く利用者の見守りや、寄り添い歩行、介護士が利用者の手を引いて歩く手引き歩行により、歩く動作を支援します。
それぞれのADL(日常生活動作)に合わせて、必要な介助方法を選択することが大切です。
移乗介助
「トランスファー」や「トランス」とも呼ばれる移乗介助は、ベッドと車イス、車イスとトイレの行き来に必要な介助です。
移乗介助を行う際も、利用者の残存機能をできる限り活用しましょう。
これは、介護士の肉体的負担の軽減にもつながります。
また、皮膚が弱い高齢者は、些細な衝撃でも内出血や擦過傷につながるため、注意して移乗介助を行いましょう。
更衣介助
更衣介助は、衣類の着脱にサポートが必要な方へ提供されます。
更衣介助の基本は「脱健着患」です。
脱ぐときは健側から始め、着るときは患側から行いましょう。
また、高齢者には腕が上がりにくい方や、肘や膝が伸びにくい方も多いため、無理に引っ張るといったことがないように注意が必要です。
介助における4段階の分類
介助を行う上では、利用者のADL(日常生活動作)を把握し、残存機能を生かすことが大切です。
介助のレベルは大きく分けると、4つの段階に分類されます。
実際には、利用者や動作によって細かな違いがあるため、経験の浅い職員は先輩職員に確認してから業務を行うようにしましょう。
自立
自立とは、特定の日常生活動作において、介助を必要とせずにすべて自力で行える状態を指します。
すべての動作が自立している状態であれば、要介護認定でも「自立」とされ、介助が不要と判断されます。
一部介助
動作内の一部において、見守りや介助が必要となる状態です。
例えば「単独歩行は可能であるが、時折ふらつきがあって見守りが必要である場合」や「入浴において洗身は自立しているが、洗髪には介助が必要である」など、部分的な支援が必要な場合が該当します。
ただし、後述する「半介助」と明確な線引きがあるわけではなく、自立と半介助の中間と思っていただければ十分です。
半介助
支えがあれば歩ける、更衣において袖を通せば首は自力で通せるなど、部分的に自力で行える方に該当します。
半介助には、残存機能を生かすことを考慮した介助が求められます。
全介助
全介助の場合は、特定の動作のすべてにおいて介助が必要です。
移乗においては体重のほぼすべてを介助者が支え、排泄においてはおむつ交換がメインとなります。
介護・介助を行う上で注意すること
介護にも介助にも共通して、重要となる視点や注意するべきポイントがあります。
これらを怠ってしまうと、利用者との信頼関係にも影響し、適切な支援が困難となることもあるため、ここで一度確認しておきましょう。
必ず声掛けを行う
介助を行う前には、利用者への声掛けが欠かせません。
急に体に触れると、不安を与えてしまうだけでなく、驚いて体に力が入ってしまう可能性があります。
しかし、声掛けをしながら介助することで、利用者は安心できて協力を得やすくなり、介助者の負担を減らすとともに、残存機能を生かした介助が可能となります。
まずは「車イスに座りましょう」「オムツを交換しましょう」など、これから行う介助の目的を伝えましょう。
その後、動作ごとに「足を下ろしてください」「横を向いてください」と具体的に説明することで、利用者は安心して協力しやすくなります。
最低限の介助で残存機能を生かす
介助を行う際には、なるべく最低限のサポートのみを行うことが大切です。
すべての動作を介助者が行ってしまうと、利用者の残存機能を十分に生かせず、長期的に見て要介護度の悪化につながる可能性があります。
利用者がどの程度自力で行えるのか、ADL(日常生活動作)を把握し、一人ひとりに適した介助法を実施することが重要です。
ゆっくりとしたペースで介助する
介助者が焦って介助を行うと、利用者は不安を感じてしまい、信頼感を損ないかねません。
そのため、ある程度余裕を持って、ゆったりとしたペースで介助することが大切です。
身体に障害がある方は、動作がゆっくりであることが多く、例えばパーキンソン病の方は意思があっても、思うように身体が動かない場合があります。
そこへ、焦るように声をかけたり、介助を急がせたりすると、不安や不信感を与えてしまうかもしれません。
利用者のペースに合わせて介助することで、利用者から協力動作を引き出し、安心して介助を受けられる信頼関係を築くことができるでしょう。
信頼関係を築くコミュニケーション
介護において、利用者との信頼関係の構築は欠かせません。
そのためには、介助者が適切なコミュニケーション方法を理解しておくことが重要です。
ポイントは、ゆっくりはっきりと話すこと、目線の高さを合わせること、相手の話をよく聞くために非言語コミュニケーションを活用することです。
相手の話すペースに合わせ、頷きや身振り手振りを交えることで、利用者は「自分の話をしっかり聞いてくれている」と感じるでしょう。
すると、双方に話しやすい雰囲気が生まれ、スムーズな会話や信頼関係の構築につながります。
その人らしい生活を支援する
介護を受ける利用者は、ADL(日常生活動作)の違いのみならず、生まれた場所や育ってきた環境、歩んできた人生など、一人ひとりで異なります。
そのため、介助者は利用者それぞれのニーズや感情を理解し、一人ひとりに適した支援を行わなければなりません。
可能な限り自己選択や自己決定を支援し、その人らしい生活を実現していくことが「介護」や「介助」には求められます。
まとめ
「介護」と「介助」という言葉は、似ていて混同しやすいですが、その意味には明確な違いがあります。
「介護」は、生活全般を支える広い概念であり、身体介護・生活援助・精神的支援などのサポートを含みます。
一方「介助」は、その中で実際に行われる具体的な支援行為のことを指します。
ただし、どちらにおいても共通して大切なのは、利用者の残存機能を生かしながら、その人らしい生活を支えることです。
過度にお手伝いするのではなく、必要な部分だけを支援する姿勢が利用者にとって、自立支援と生活の質の向上へとつながります。
また、声掛けや適度なコミュニケーションを心がけることにより、利用者の安心感を高め、信頼関係を築くことが可能です。
これらが結果として、より良い介護・介助ケアの実現へと結びつくでしょう。