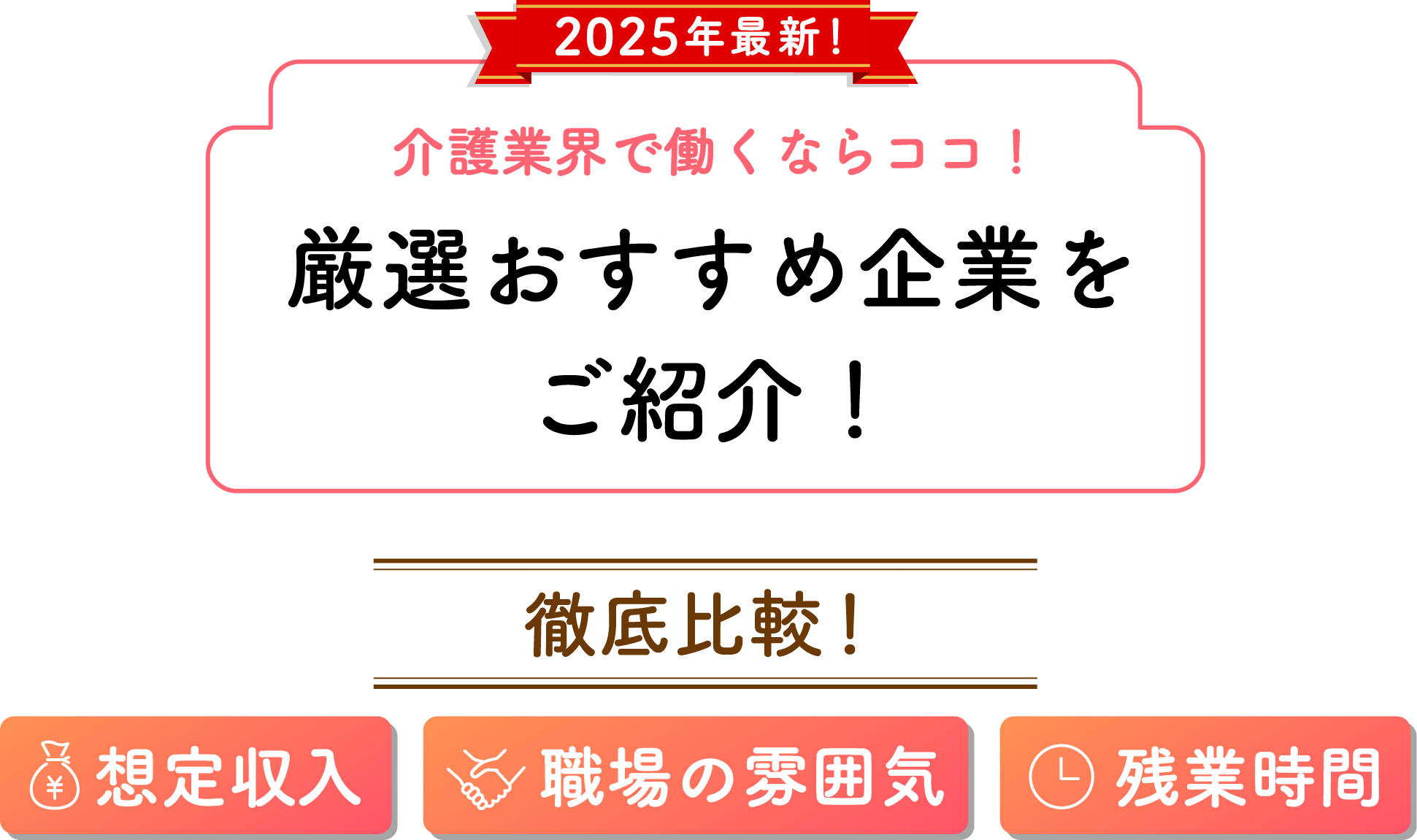「ケアマネってどんな資格?」「取得にどのくらいかかるの?」など、ケアマネの資格について気になっている方も多いのではないでしょうか。
ケアマネの資格試験を受験するには、一定の実務経験が必要です。
このことから、資格を取得すると、さらなるキャリアアップにつながります。
そこで本記事では、ケアマネ(介護支援専門員)の仕事内容から、資格取得にかかる期間、試験の概要、資格取得のメリットまで詳しく解説します。
ケアマネの資格を取り、キャリアアップしたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
ケアマネ(介護支援専門員)はどんな職業?
介護の仕事には、ホームヘルパーやソーシャルワーカー、介護福祉士など、さまざまな仕事があり、今回紹介するケアマネ(介護支援専門員)もその一つです。
ここでは、ケアマネの仕事内容や求人の探し方をお伝えするとともに、向いている人や将来性についても解説していきます。
将来ケアマネとしてキャリアを形成したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
ケアマネ(介護支援専門員)とは
「ケアマネ」とは、ケアマネジャーの略称で、正式名称は「介護支援専門員」です。
ケアマネになると、さまざまな職場で幅広く業務ができます。
また、居宅介護支援事業所で働く場合は「居宅ケアマネ」、介護施設に勤務する場合は「施設ケアマネ」と区別して呼ぶこともあります。
ケアマネは、実際に利用者の介護を行うというよりも、要介護者のケアプランを作成したり、各機関や施設との調整をしたりするなどの業務を担っており、利用者と介護サービスの架け橋のような存在です。
なお、この資格は国家資格ではなく、お住まいの都道府県で認定・交付されています。
仕事内容
ケアマネの仕事は、主に2つあります。
1つは、ケアプランの作成です。
ケアプランとは、利用者とその家族が置かれている状況や希望を踏まえ、どのような方針で介護サービスを提供し、問題を解決していくのかを計画するものです。
ケアマネは、利用者それぞれに合わせて適切なプランを作成し、定期的に見直すなどの管理業務を行います。
2つ目は、各介護サービスとの調整業務です。
具体的には、作成したケアプランに基づき、利用者が介護サービスを受けられるように情報を提供するとともに、施設や現場スタッフとの連携を図ります。
そのほかにも、介護保険サービスの利用における介護給付の管理や、市町村が委託した要介護認定の調査を行うこともあるようです。
働き方
ケアマネの勤務先は、居宅介護支援事業所と老健や特別養護老人ホームの2つに分かれ、どちらで働くかによって仕事内容や働き方も異なります。
居宅介護支援事業所に勤務する場合は、主に在宅介護を希望する利用者のケアマネジメントを行います。
利用者は自宅で生活するため、訪問サービスやデイサービス、ショートステイといった短期入所サービスを利用することから、さまざまなサービス提供業者との連携が不可欠です。
一方、介護施設に勤務する場合は、その施設に入所している利用者のケアマネジメントを行います。
そのため、在宅介護の利用者向けケアプランとは内容も異なり、施設で提供されているサービスを活用したプランの作成が求められるでしょう。
給料
厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」では、令和5年と令和6年のケアマネの平均給与額が公表されています。
この調査結果によると、令和5年の平均給与額は常勤で363,760円、令和6年は常勤で375,410円と、1年で11,650円上昇したことが分かっています。
この金額は、令和6年の常勤介護職員の平均給与額である338,200円より数万円高く、ケアマネの資格を取得することにより、給与が上がる可能性があるといえるでしょう。
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況調査結果」
求人の探し方
ケアマネの求人を探すときは、自分に合う職場環境や利用者との関わり方、待遇などの軸を明確にした上で、介護職を専門に扱う求人サイトを利用しましょう。
例えば、ケアマネとして働くと言っても、居宅介護支援事業所にするか、介護施設にするかにより、主な業務内容やスタッフ・利用者との接し方が大きく異なります。
そのほかにも、自分のライフスタイルに合う雇用形態や収入の目標額など、妥協せず理想の条件に合う職場を吟味することで、より快適に働ける環境を見つけられるはずです。
やりがい
ケアマネの主な仕事は、ケアプランを作成することですが、時には実際に身体介護を行うこともあります。
そのため、利用者と関わる機会が多く「ありがとう」といった感謝の言葉は、やりがいとなるでしょう。
また、自分が提供した情報や作成したプランにより、利用者の状態が改善したときにも、やりがいを感じられるはずです。
このように、利用者や家族と密接に関わり、親身にサポートできるのはケアマネならではの魅力といえます。
ケアマネ(介護支援専門員)に向いている人
ケアマネに向いている人の特徴の一つは、タスク管理能力が高いことです。
ケアマネには、利用者が抱えるさまざまな問題に対して、優先順位をつけて解決することが求められます。
また、円滑に介護サービスを提供するために、スケジュールやタスクを調整する能力も必要です。
さらに、プランの作成や実施に当たって、利用者やその家族と面談したり、多くのスタッフと連携を図ったりしなければいけません。
そのため、自らコミュニケーションを取れる積極性が重視されます。
ケアマネ(介護支援専門員)の将来性
結論から言うと、ケアマネに将来性はあると考えられます。
厚生労働省のホームページに掲載されている「我が国の人口について」では、65歳以上の人口は今後人口全体の30%を超えると予想されており、介護を必要とする高齢者も増加する可能性が高いためです。
また、ケアマネには、利用者や家族から抱えている問題やニーズについて、丁寧にヒアリングする必要があります。
そのため、近年発達してきているAIに仕事を取られる可能性も低いといえるでしょう。
出典:厚生労働省「我が国の人口について」
ケアマネ(介護支援専門員)になるには最短でどのくらいかかる?
ケアマネになるまでの期間は、介護職に関する資格を保有しているか、または実務経験があるかによって異なります。
ここでは、ケアマネになる方法と、置かれている状況別でかかる期間を解説していきます。
ケアマネ(介護支援専門員)になるには
ケアマネになるには、まず「介護支援専門員実務研修受講試験」の受験資格を満たさなくてはいけません。
その上で、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、研修を修了すると、晴れてケアマネとしてのキャリアを開始できます。
そのため、ケアマネの資格を取得したいと考えている方は、早めに受験資格を確認し、計画的に準備を進めていくのがおすすめです。
受験資格がある場合
すでに受験資格を満たしている場合は、1年ほどで取得が可能です。
試験合格までの勉強期間は約180日ですが、試験は年1回しかなく、合格後も研修受講や各種手続きが必要なため、余裕を持って計画しておくと安心です。
また、ケアマネの資格試験は看護師や准看護士、社会福祉士などの国家資格を取得している人も、実務経験が5年以上あれば受験できます。
介護福祉士資格を保有している場合
受験資格となる実務経験がなくても、国家資格の介護福祉士を取得している場合は、介護福祉士として5年間の実務経験を積むことで、試験に挑戦できます。
なお、この5年の実務経験に関して、雇用形態の指定はありません。
そのため、正社員ではなくパートや派遣などでの実務経験も加算できます。
しかし、実務経験が5年以上あることに加え、従事日数が900日以上であることも必須条件となっているため、休業期間などがある場合は注意しましょう。
未経験から受験する場合
完全未経験からケアマネになるには、最短で8年かかります。
これは、ケアマネ試験を受けるには介護福祉士などの国家資格が必要であり、介護福祉士取得には実務者研修の修了と3年以上の実務経験が求められるためです。
介護福祉士になるのに3年、ケアマネ試験の受験資格である介護福祉士になってから5年の実務経験を積む必要があるため、合計で最短でも8年はかかる計算となります。
資格試験の概要
受験するまでに長い期間を要するケアマネの資格試験ですが、具体的にどのような試験なのでしょうか。
ここでは、資格試験の概要について詳しく解説していきます。
これから受験をしようと検討している方は、ぜひ参考にしてください。
資格の取得方法
ケアマネの資格は、介護支援専門員実務受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了することで取得できます。
ただし、この試験を受けるためには、いくつかの受験資格を満たしていなければなりません。
思い立ったときにすぐ受験できる試験ではないため、計画的に準備を進めましょう。
資格の受験資格と実務経験年数
試験の受験資格は、特定の国家資格に基づく業務か相談援助業務のいずれかに従事しており、5年以上かつ従事日数が900日以上あることです。
これらは必須条件ですが、都道府県ごとに別途条件がある可能性もあるため、自分が受験する都道府県の受験要項は必ず確認しておきましょう。
資格の試験内容
ケアマネの資格試験では、介護支援分野と保健医療福祉サービス分野の2つの分野から出題されます。
問題数は介護支援分野から25問、保健医療福祉サービス分野から35問の全60問で、試験時間は120分です。
また、多くの都道府県が5択から複数の解答を選択するマークシート方式を採用しています。
資格の試験日程
ケアマネの資格試験は例年10月に行われており、11月下旬から12月上旬に都道府県のホームページや郵送される通知にて合格発表されます。
なお、東京都の場合、郵送される合格通知は合格発表日に発送されるため、早く結果を知りたい方はホームページを確認するとよいでしょう。
資格の受験費用
ケアマネの資格試験の受験料は、受験する都道府県によって異なります。
例えば、受験者が多い主要都市を見ると、東京都の場合は払込手数料を含めて12,400円、神奈川県では13,400円、大阪府では13,570円です。
受験直前に困らないためにも、あらかじめ住んでいる都道府県の受験料を確認しておきましょう。
資格の合格率や難易度
令和以降、ケアマネ試験の合格率は20%前後に落ち着いており、受験者の5人に1人しか合格できない難しい資格として知られています。
令和7年度試験では合格率が32.1%となり、約20年ぶりに30%を超える結果が出ましたが、それでもほかの介護系資格と比較すると難易度の高い資格です。
出典:厚生労働省「第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」
資格取得の流れ
確実にケアマネの資格試験を受験するためには、計画的に準備を進めていくことが大切です。
先述したように、ケアマネの資格試験は年に1度しかなく、これを逃すと次の試験は1年後となってしまいます。
そのため、問題なく受験できるよう、資格取得までの流れをきちんと理解しましょう。
ここでは、資格取得までの流れと合格後の流れに分けて、詳しく説明していきます。
試験受験から合格までの流れ
まずは、4〜5月ごろにお住まいの都道府県で、受験要項や願書などの必要書類を受け取らなくてはいけません。
受験日の約半年前から動き出す必要があるため、忘れないように注意しましょう。
その後、必要書類を記入したら期日までに手続きを行い、受験の申込みをします。
ここで必要となる「実務経験(見込)証明書」は、前もって勤務先に発行してもらわなくてはいけないため、早めに手配しておきましょう。
定められた手順で申し込めたら、試験当日の約1カ月前に受験票が届き、10月に試験が行われます。
合格した後の流れ
試験の合格後は案内に従い、介護支援専門員実務者研修を修了しなくてはいけません。
この研修を修了し、介護支援専門員資格登録簿への登録や、介護支援専門員証の交付申請を行うと、ケアマネとして働けるようになります。
ただし、介護支援専門員資格登録簿の登録申請は、研修を修了した日から3カ月が経つと登録できなくなるため、早めに申請しましょう。
ケアマネ(介護支援専門員)の資格を取得するメリット
ケアマネの資格取得は難しく、受験資格を満たすまで時間がかかりますが、得られるメリットも多いことから、取得して損はありません。
ここでは、ケアマネの資格を取得して得られるメリットについて、具体的にご紹介していきます。
介護職での就職に有利である
ケアマネの資格を取得していると、専門的な介護の知識を持ち、利用者に合わせた介護計画を立てられることを証明できます。
試験の難易度が高く、ごく少数の限られた人しか持っていない資格であるため、介護業界であれば非常に重宝されるでしょう。
キャリアアップや収入アップにつながる
ケアマネの資格を取得することで、介護業務のなかでもケアプランの作成や外部との連携など、より責任のある仕事を担当できるようになります。
また、専門性の高い資格であるため、施設内での信頼を得やすく、リーダー職などの役職が与えられることも珍しくありません。
また、給与面でも基本給が上がったり、資格手当がもらえるようになったりする可能性があります。
まとめ
ケアマネ(介護支援専門員)として働くには、保有資格や実務経験など、受験資格を満たした上で、資格試験を受けて合格する必要があります。
無資格からでも挑戦できますが、最短でも約8年かかる難易度の高い資格です。
しかし、取得すれば業務の幅が広がり、給与や待遇の向上にも期待できます。
介護業界でキャリアを築き、長く安心して働きたい方にとっては、目指す価値のある資格といえるでしょう。
ぜひ、本記事を参考に、ケアマネ(介護支援専門員)の資格試験を検討してみてはいかがでしょうか。